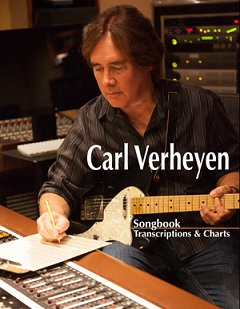スティーヴ・ヴァイのバンドのベーシストとして数々のアルバムやG3ツアーへの参加、他にもヌーノ・ベッテンコートのPopulation1における日本公演での助っ人ベーシストとして素晴らしいパフォーマンスを披露し注目を集めたフィリップ・バイノー。
今回のコラムではツアーに挑むための事前準備から本番当日におけるサウンドチェックに至るまでに何をすべきかをフィリップが伝授してくれる。
ドイツからこんにちは!
現在、WARLORDというバンドのツアー真っ最中のフィリップ・バイノーです。
僕はスティーヴ・ヴァイのベーシストとして知られていることが多いが、スティーヴ・ヴァイがオフの時や、別のプロジェクトで忙しい時(ちなみに現在はオーケストラのツアーを行っている)は、僕も別のアーティストの仕事に参加することができる。
ツアーの準備
どんなアーティストの仕事であっても、ステージに上がる前は必ず曲を覚える。僕が曲を覚える時のプロセスはこんな感じだ:まず、最初は楽器を持たずに曲を聴く。曲の雰囲気や構成に集中して、できる限り細かい部分まで吸収するように心がけている。次に譜面を書く。これは非常に重要なステップだ。譜面を書くことによって自然に曲を覚える作業に入っている訳だ。実際に楽器を持って練習するのはそれからだ。
次に音源を聴きながら、その音を再現できるようなフィンガリングを探す。それが決まったら、今度は毎日の練習スケジュールを決める。これが鍵だ!自分で決めた練習スケジュールは必ず守る。練習のための時間を作って、そのスケジュールをきっちりと守ることは非常に重要なことだ。曲を早く覚えることができるし、曲の細かい部分まで気が回せるようになる。勿論、曲の数によっていつ練習をスタートさせるか、どれくらいの期間練習を続けるかを決めるようにしている。
さあ、これでバンドとリハーサルができる!
曲を覚えていても、リハーサルには必ず自分が書いた譜面を持参している。リハーサル中にアレンジが変わることもあるし、アーティストがレコーディングとは異なるアレンジをリハーサルで提示してくることもあるからね。曲にエンディングが付け加えられたり、曲構成が変えられたりした場合は必ず譜面にメモをするようにしている。そうすることによって次の機会に同じ曲を演奏することがあればそのメモを参照することができる。
それと、リハーサルには必ず何らかの録音機器を持参するようにしている。リハーサルを録音することによって、リハーサル後に演奏を復習することができる。これは曲を覚えるために非常に役立つことだ。
ちなみに、リハーサルの時に工具箱を持参するのも重要だ。自分の仕事に対して前向きかつ真面目な姿勢を見せるのも大切だし、現場の人たちに一緒にいて楽しいと思ってもらえるのも大事だ。別にそういう雰囲気を無理に作れという訳じゃないんだ。でも、周りの人たちから用意周到でプロ意識を持ったミュージシャンだという評価を得ることによって仕事も増えるはずだし、仕事そのものも楽しくなるはずだ。

準備はできた。さあ、本番だ!
本番で自分のアンプを使う場合は特に音作りの問題はない。でも、僕がライヴをやる時はアンプ等の機材が既に用意されている場合もある。こういった場合、音作りを短時間で決めないといけない。
僕はこのようなステップで音作りをしている:
1) まず機材のベーシックな部分が全て調っているかどうかをチェックする。アンプの電源ケーブルがささっているかどうか、スピーカー・ケーブルがささっているかどうかを確認した上で電源が入ることをまずチェックする。あたり前のように聞こえるかもしれないが、これを習慣づけることによって単純なミスを防ぐことができる。
2) 僕はまずベースをアンプに直で繋げている。この時点ではエフェクターやペダルは一切使っていない。使うのはアンプ、ケーブル、そしてベース本体のみだ。アンプのEQはまずフラットにしてから必要なところだけを足していく感じだ。アンプから2〜3メートル離れると音は変わるので、最初に低音を出し過ぎないように心がけている。まずはバランスの良い音を作るのが大切だ。そうすれば、後から音量を上げたい場合は全体のボリュームだけを上げればいい訳だ。それに、小さい音量で演奏しないといけないシチュエーションでも良い音のバランスのまま音量を下げることができる。
3) 次に本番で使うペダルボードやエフェクターを繋げてPAスピーカーから出る音や客席内の音を確認する。モニターから自分のベースの音を返してもらう場合はこの時点で返してもらうといいだろう。ここで注意したいのはアンプとモニターから出ている音量のバランスだ。ベースの音が大きくなり過ぎるとステージ上は大変なことになるからね。自分にとっていい音だと思っていても、他の人にとっては大きすぎる場合があるから注意するように。個人的にはモニターからベースを一切返さないようにしている。アンプからの音だけにしている。そうすることによって、ベースの音を全て自分でコントロールできることになる訳だ。PAエンジニアは基本的にプレイヤーの出す音を調整するのが仕事だ。ひとつアドバイスするなら、ステージ上の音量は自分の演奏に支障をきたさない程度に可能な限り小さくすること。そうすることによってPAエンジニアはPAスピーカーから出す外音のベースの音量を上げてくれる。結果的に大きなベース・サウンドに繋がり、自分も演奏しやすくなる訳だ。
4) ウォーミング・アップに関しては人それぞれやることが異なる。小さなアンプを楽屋に持ち込んで本番前に30分〜1時間練習する人もいる。以前、iPadやiPhoneのアプリでAmpliTubeというアプリを使ったことがある。変換プラグを使ってベースを繋げればヘッドフォンで好きなだけ練習できるというものだ。自分の本番前のウォーミング・アップはその日に演奏する曲のおさらいをするぐらいだ。常に自分の頭の中で曲を新鮮な状態にしておきたいからだ。それと、集中力を高めるために本番前に10分ほど瞑想するようにしている。椅子に座り、両足を床に置いて、目を閉じて心を無にしながら今という瞬間を感じるようにする。僕のミュージシャンとしての目標は演奏をしながらひとつの瞬間から次の瞬間へと動くことだ。間違えやミスのことを考えたり、他人が何を考えているか等に集中力を奪われてはいけない。ステージの上にいる限りは常にベストを尽くすのみだ。勿論、間違えやミスをしてもいいという意味ではない。でも、誰でもミスはするものさ。一カ所、二カ所ミスをしたところでコンサート全体がダメになる訳じゃない。でも、ダメになる時もある!僕にだってその経験はあるよ。ウォーミング・アップが終わったら着替えて、履き心地のいい靴を履く。本番中はずっと立っているからね。細かいことに集中力を奪われないようにしないといけない。
5) 最後に自分の楽器の話をしよう。ベーシストとしてのキャリアの中で僕は今までにキーボード・ベースからウクレレ・ベースまでコンサートで求められているサウンドを忠実に再現するために様々なベースを使ってきた。スティーヴ・ヴァイとプレイする時は様々な音を出すためにペダルボードを使っている。僕のウェブサイト(www.philipbynoe.com)を見てくれれば最新のペダルボードの写真がアップされている。音量をだすためにMORLEYのVolume Distortion、ベース間の切り替えに便利なMORLEYのA/B Box、パンチのある歪みを出すためにTC ELECTRONICのMojoMojo Overdrive、TC ELECTRONICのポリ・チューナー、TC ELECTRONICのCorona Chorus、ファンキーなシンセ系の音を出すためにBOSSのBass Synthesizer、そしてLINE 6のワイヤレスを使っている。これらのペダル類はG-LABのパワー・サプライを使って電源の供給をしている。スティーヴ・ヴァイとプレイをしている時のペダルボードはこんなセッティングだ。ちなみに今はWARLORDのツアーに参加しているけど、彼らとプレイする時はペダル類を一切使わない。そのアーティストやショウに何が必要かをよく見極めて自分の機材を選ぶことを勧める。他にもSteve Fisterのバンドでプレイすることもあるけど、その時にはまた全く違ったペダル類を使っているし、時にはアップライト・ベースを使うこともある。JAMBOという子供向けの音楽を演奏するバンドではウクレレ・ベースを使っている。

今までの経験から、緊張に対する最も効果的な対処法はきっちりと準備をすることだ。本番のことが不安になるのであれば、演奏する楽曲を徹底的に覚えることだ。友人がこんなことを言っていた:「きっちりと準備をしていれば、酷い演奏をする訳がない。」僕も同感だ!
このコラムを読んで少しでも僕のミュージシャンとしての世界の理解してもらえたら嬉しいよ。ともかく、ショウに臨む時は十分に準備をすること。そうすればきっと楽しめるだろうし、またお誘いも増えることだろう。音楽でメシを食うのはとても大変なことだ。だからこそ、どんな仕事やショウに対しても正しい選択をすることを心がけるべきだ。そうすれば、ミュージシャンとして生計を立ていくことも夢じゃないし、音楽を楽しむことができるだろう。
フィリップ・バイノー
Philip Bynoe
<Philip Bynoe コラム>
Translation by Louis Sesto (EAGLETAIL MUSIC)