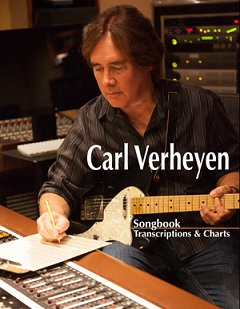Keith Scott

Photo by Mike Blake
ブライアン・アダムスの数多くのアルバム、そしてライブにおいて、巧みなギタープレイで彼を支え続けている長年の相棒、それがキース・スコットだ。彼のギタープレイは、派手な速弾きや奇抜なテクニックに頼るのではなく、ブライアンの歌と見事に調和するメロディを紡ぎ出すセンス、ダイナミクスのあるトーンを生み出す繊細なピッキングなど右手の高度なコントロール、そして「ロックにおけるリズムギターはこうあるべきだ」というお手本のような骨太なリズムワークで構成されており、まさにロックギターの本質で勝負するタイプのミュージシャンである。
ブライアンの新作『ROLL WITH THE PUNCHES』では、ブライアン自身がギターを含め多くの楽器をこなしている中、4曲でキースがギターを担当(アルバムのブックレットには3曲でLEAD GUITAR、1曲でGUITARの表記がある)。その巧みなプレイが、ファンが求める“ブライアン・バンドらしさ”と、さらなる躍動感をもたらしている。キース・スコットに話を訊いた。
Interview / Text Mamoru Moriyama
Translation Hiroshi Takakura
Muse On Muse (以下MM) : ブライアンの新作『ROLL WITH THE PUNCHES』は前作までと同様にバンドでのレコーディングというよりもブライアン自身が多くの楽器パートをマルチにこなし、必要に応じて他のプレイヤーに特定のパートを任せています。 このことについてあなたはどのように感じていますか。
Keith Scott (以下KS) : ブライアンの音楽に関しては、他のミュージシャンがいるかどうかに関係なく、どうするか決めるのは彼自身だね。プロセスではなく最終的に曲がどう仕上がったかが一番大事だから、彼自身がその結果に満足しているなら、それで十分だと思うよ。
MM : 『カッツ・ライク・ア・ナイフ』や『レックレス』などライブ感溢れるロック作品がリリースされた80年代から今作がリリースされたこの2025年までには40年以上が経過しています。当時と今でアルバム制作やレコーディングの過程でどのような違いを感じていますか。
KS : ライブミュージシャンがスタジオに集まって一緒にプレイする、あの時代はポピュラー・ミュージックの多くがそういう作り方だったんだ。テクノロジーの進化によって、音楽の作り方やプロデュースの方法は大きく変わったね。さらに今度はAIが台頭してきたから、30年前にデジタル録音やコンピューター録音が出てきた時と同じように、レコーディングのプロセスはまた変わっていくはずだよ。
MM : 今回のアルバムでは全10曲中の4曲であなたはギターを弾いています。ブライアンはそれら4曲においてあなたにギターを依頼する際、ギタープレイについてはどのようなオーダーを出しましたか。
KS : ほとんどの場合彼は何も言わないんだ。「この曲で君ならどう弾く?」って聞いてくるくらいで、まずは自由に試させてくれる。それがハマることもあれば、そうじゃないこともある。
でも、彼の中にこの曲には僕のギターが合うというイメージがあって、そういう時に呼んでくれているんだと思う。
MM : ロバート・ジョン・”マット”・ラングがプロデューサーを務めていますが、彼からはギタープレイやサウンドに関して何かインプットはあったのでしょうか。
KS : 少しだけあったね。特に「Will We Ever Be Friends Again」のパートについて、彼は今スイスに住んでいて、僕とブライアンはバンクーバーのWarehouse Studioにいたから、Zoom上で、彼がギターパートを歌いながらアイデアを共有してくれたんだ。
MM : アルバムのリリースに先行し、最初にミュージックビデオが公開された「ROLL WITH THE PUNCHES」では、曲が持つ力強さ、そして曲の後半においてあなたのリードギターはロック魂が全開です。
KS : この曲は当初いくつか別のバージョンがあったんだ。最終的にアウトロを倍のテンポにしたことによってよりエネルギッシュになった。あれはブライアンのアイデアだね。自分としてはGuns N’ Rosesみたいなエナジー感があったら面白いなと思っていて、結果としてそんな感じになったと思うよ。
MM : 「MAKE UP YOUR MIND」は軽快なテンポで清涼感のある曲であり、あなたのギターも曲に絶妙なオブリガードを加え、雰囲気を盛り上げています。
KS : この曲でも、ブライアンはもう少しエネルギーが必要だと思っていたようだね。そこでストラトキャスターをそのままアンプに挿してThe Whoの「Going Mobile」をイメージしてギターを弾いてみたんだ。
MM : あなたが参加している4曲中の3曲ではLead Guitarとしてクレジットされていますが、「BE THE REASON」ではGuitarとしてクレジットされています。ブライアンも同じくGuitarパートでクレジットされていますが、この曲におけるブライアンとあなたのそれぞれのギターパートの分担について教えて下さい。
KS : この曲では、彼はあのギターのフックのメロディーをもっと強調したかったんだと思うよ。アレンジ自体はすでにできていたから全体のエネルギーをもう一段押し上げる、という役割だったんじゃないかな。

Photo by Mike Blake
MM : アルバムの中での楽曲のレコーディング、そしてライブにおいてもブライアンもギターを弾きますが、あなたとブライアンでともにリズムギターを弾く際においてプレイ面での役割分担はどのように行われるのでしょうか。
KS : 自分はなるべくブライアンと違うレンジを弾くことを心がけていて、リズムというよりはラインを意識している。ブライアンはすごく強力なリズム・プレイヤーだし、メロディを奏でるのも上手いんだ。でも彼は歌いながら弾いているから、どうしてもボーカルの伴奏がメインになる。そこで僕は、その周りをうまく埋めながら必要なところでそれを引き立てる、というイメージでプレイしているよ。
MM : アルバムのエンディングを美しく飾る「WILL WE EVER BE FRIENDS AGAIN」では、少ない音数でありながらも聴き手の感情に突き刺さるあなたによるギターのフレーズが印象的です。
KS : このアルバムの中でも恐らく一番好きな曲だね。80年代のロック・バラード的な曲だけど自分にはすごく“マット・ラングらしい”感情やムードが詰まった曲に感じられるんだ。最初はとてもシンプルな形だったんだけど、そこに少しずつ色々な要素が足されていった。最終的には、ソロのパートはほとんどマットが組み立ててくれたような感じになった。彼の中には、はっきりとしたこういう音にしたいというイメージがあったんだと思う。あのトラックを録るのは本当に楽しかったし、仕上がりにとても誇りを持っているよ。ソロを弾く側として、「こうなってくれたらいいな」と願うような形になったね。
MM : あなたがギターをプレイしている前述の4曲についてのレコーディングはどのように行われましたか。
KS : 自分が弾いたパートは2023年以降に何度かに分けて、ブライアンのバンクーバーのスタジオで録ったものなんだ。あるセッションで何曲かまとめて録ったり、別の日にまた別の曲を録った曲もあるね。その頃はツアーでも忙しかったから、その合間を縫ってスタジオに入る日を確保していった感じだね。
MM : 今作において使用しているギターやアンプ、ペダル等の機材を教えて下さい。
KS : ほとんどの曲で弾いているのは、ブライアンの1964年製フェンダー・ストラトキャスター(キャンディ・アップル・レッド)だと思う。例外としてはタイトル曲「Roll With The Punches」のアウトロで、そこだけは彼の1960年製ギブソン・レスポール・サンバーストを使った。アンプは、1960年代後期で20ワットのマーシャル・コンボ(12インチのセレッション2発)か、1950年代後期のフェンダー・ツイード・Harvardがメインに使用した。時々ブライアンの100ワットのマーシャル・プレキシ・ヘッドを、ヴィンテージの4×12のマーシャル・キャビに繋いで使うこともあったね。それにDIでドライの信号も録音しといて後からモデリングやエフェクトを足しやすいようにしていた。アンプはどれもSennheiser 421とShureのSM57でマイキングして、必要に応じてRoyerのリボン・マイクも足していたよ。
MM : あなたのサーフミュージックのプロジェクトであるTHE FONTANASについて2作目となるアルバムがほぼ完成の状態だと以前に聞いた記憶があるのですが、現在の状況を教えて下さい。
KS : そうなんだ。Fontanasの2作目はすでに完成していて、同じ名義で自分プロデュースのクリスマス・アルバムも作った。どちらも去年2024年にリリースしているよ。
MM : 2026年1月にはブライアン・アダムスの日本公演ですね。公演を楽しみにしているファンへメッセージをお願いできますか?
KS : もちろんだよ!僕たちは1983年から日本でツアーをしてきていて、また日本のみんなに会えるのを本当に楽しみにしているんだ。日本のファンには、長い間変わらずサポートしてもらっていて心から感謝している。来年頭にライブ会場で会おう!